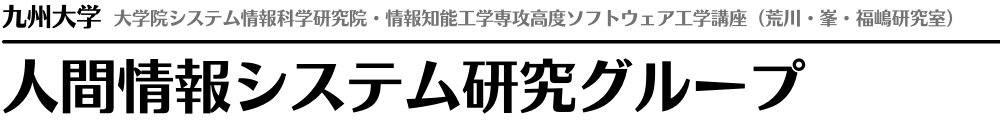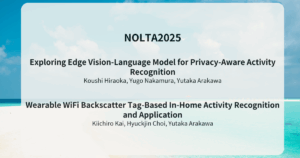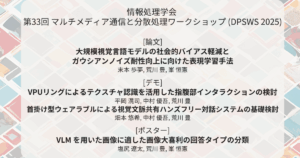ADMA 2025・参加報告(Lee Liu Cheng)

学会情報
- 参加した学会名
- 開催場所
- 京都
- 日程
- 2025/10/22 - 2025/10/24
- 報告者
- Lee Liu Cheng
発表概要
- タイトル
- Emerging Trends in Knowledge Tracing Models: A Technical Survey from 2022 to 2025
- 内容
本研究は、学習者の知識状態を時系列的に推定する「Knowledge Tracing(KT)」モデルの最新動向(2022–2025年)を体系的に整理・分析したサーベイである。特に、従来の研究では十分に比較・検証されていなかった複数のモデルを同一環境下で再実装し、行動特徴(問題の難易度、学習者の能力、反応速度、ヒント使用など) を考慮した包括的な評価を行った。
本研究では、近年のKTモデルを6つの方向性に分類し、それぞれの特長と限界を明確化した:
メモリベース構造
グラフ構造モデル
アテンション機構
説明可能性指向モデル
多関係推論モデル
自動化/個別化(Automated / Personalized)モデリング
特に6番目の「Automated / Personalized」カテゴリーでは、学習者ごとの特性を自動的に学習し、リアルタイムに知識状態を更新できる表現学習手法(representation learning)の重要性を示した。
また、本研究では、異なる行動特徴の組み合わせ(例:「低能力×易しい問題×反応遅い」など)に対して、各モデルの性能変動を比較し、モデルの安定性・適応性を実証的に分析した。その結果、アテンションベースモデル(特に ATKT) は複数特徴が干渉する条件下でも最も安定した性能を示した一方、多関係メモリモデル(DKVMN-KAPS) は構造化された高難度場面で優位性を示した。
今後の課題としては、より多様な教育データセット(EdNet、Junyi Academy など)への拡張に加え、行動特徴をリアルタイムで検出・適応できる動的アーキテクチャの開発、およびマウス軌跡・キーボード操作・視線・身体動作などの学習行動データを統合した マルチモーダル知識追跡 の実現を目指している。
質疑内容
Q: 今後の展望として「Automated / Personalized」方向の研究を挙げられていましたが、具体的にどのような拡張が可能だと考えていますか?
A: 本研究では行動特徴(難易度、能力、反応時間、ヒント使用)を基礎に分析しましたが、今後はよりリアルな学習環境データを取り込むことを検討しています。例えば、オンライン学習プラットフォームでは マウスの動き、キーボード入力速度、視線、姿勢変化など身体的・行動的信号 が取得可能です。これらを知識追跡モデルに統合することで、学習者の集中度・疲労・理解状態をより精密に把握でき、動的に個別化された学習支援 が実現できます。
また、表現学習(representation learning)を活用して、これらの複雑な行動データを統合的に特徴化することで、「自動化された特徴検出」と「個人最適化推定」の両立を目指します。
体験記
【2025/10/21 (火) 1日目】
初日に京都に到着し、夕日が街並みに差し込む景色がとても美しかったです。
ただ、観光客も非常に多く、とてもにぎやかでした。
峯先生のご紹介で、九大を卒業して現在はNAISTで助教をされている先輩と食事をしました。
先輩が京都近郊の本格的な中華料理の名店に連れて行ってくださり、
辛い料理が大好きな私は、日本で初めて本当に辛い料理を食べることができました。
さらに、タピオカも飲むことができて、本当に嬉しかったです。
食事の間には、先輩とさまざまなお話をすることができ、とても有意義な時間でした。
【2025/10/22 (水) 2日目】
ADMA学会が正式に開幕しました。
会場は京都大学の百周年記念館です。


【Keynote 1】
Chair: Masatoshi Yoshikawa(大阪成蹊大学)
Speaker: Hisashi Kashima(京都大学)
Title: Human-AI Collaboration for Data-Driven and Collective Decision Making(データ駆動型および集団意思決定における人間とAIの協働)



| 項目(項目名) | 重要ポイント(Key Points) | 簡単な説明(Simple Explanation) |
| 研究目的 | AIを活用して人間の意思決定をどのように向上させるかを探究した研究である。 研究の方向性としては、人間の評価から表現を学習する手法、XAI(説明可能なAI)に対する人間の理解度評価、そしてAIを用いた集団意思決定の支援などが含まれる。 | AIはもはや単にデータを計算するだけの存在ではなく、人間とともに意思決定を行い、さらには人と人との意見の調整を担う存在へと進化している。 |
| 人間のバイアス問題 × Crowdsourcing(クラウドソーシング) | 人間は判断を下す際にしばしば偏り(バイアス)を持つ。 例えば、画像を見たときに色や背景の影響を受けるなどである。 しかし、ラベルが完全でなくても、人間の主観的な「類似性判断」を活用することでAIに学習させることができる。 | AIに「2つの顔の表情がどの程度“怒っている”ように見えるか」を学習させるとする。 |
| XAIゲーム評価(Peek-a-Boom など) | AIの「説明(Explanation)」が本当に役立っているのかをどう測るか。 これは単なる正答率では評価できない。 | 「Peek-a-Boom」ゲームでは、AIが画像の一部分(AIが重要と判断した領域)だけを人間に見せ、 プレイヤーが「この画像は何か」を当てる。 もしプレイヤーがより早く、正確に答えられるなら、 AIの可視化(たとえば GradCAM)が本当に意味のある部分を示しているといえる。 実験結果から、GradCAM による「注目領域」が最も人間の理解を助けることが示された。 |
| Neural-RR モデル(公平な資源分配問題) | 限られた資源を複数人で共有する際に、どうすれば「公平かつ効率的」に分配できるか。 | 10人の学生に5つの寮の部屋を割り当てるとする。 それぞれの好み(通風、大学からの距離など)は異なる。 Neural-RR モデルは、各人の嗜好を考慮して割り当てを計算し、 全員が「他人の分配結果を過度にうらやまない」ようにする(これを EF1:Envy-Free up to one item という)。 同時に、全体の満足度(Social Welfare)も最大化できる。 この仕組みは、教育資源や医療資源などの社会的配分問題にも応用できる可能性がある。 |
| LLM-AHP システム(LLMによる意思決定分析の強化) | AHP(Analytic Hierarchy Process) は、複数の選択肢を比較して優先度を決定する手法である。 しかし、評価基準の設定や重みづけは人手で行う必要があり、時間がかかり主観的である。 | 「どの研究室が博士後期課程に最も適しているか」を決める場合を考える。 従来のAHPでは、研究テーマ・指導教員・研究費・所在地などの項目を人間が設計し、 それらを手動で比較して順位を決める必要がある。 一方、LLM-AHP は大規模言語モデル(例:ChatGPT)が自動的に評価基準を生成し、 「研究テーマ vs 研究費」などのペアワイズ比較を行って、最終的なスコアを出す。 これにより、意思決定プロセスがより迅速かつ柔軟になり、 状況に応じて自動的に基準を調整できるようになる。 |
【Tutorial 1】
Speaker: Kyosuke Nishida、Kosuke Nishida、Ryota Tanaka(NTT株式会社)
Title: Recent Advances in Large Language Models and Vision-and-Language Models
(大規模言語モデルおよび視覚言語モデルの最新動向)




| 項目(項目名) | 重要ポイント(Key Points) | 簡単な説明(Simple Explanation) |
| 研究目的 | LLM(Large Language Models)と Vision-and-Language Models(VLM)の最新技術動向を整理し、AIがどのように推論・理解・視覚的認識を発展させてきたかを解説。 | AIが「言語」だけでなく「視覚情報」も理解できるようになり、人間のように考え、説明し、行動する方向へ進化している。 |
| LLMの進化(Instruction-Tuning と RLHF) | 大規模言語モデルは、単に大量データで学習するだけでなく、人間の指示に従うように最適化されている。特に DPO(Direct Preference Optimization)が PPO より効率的に学習可能。 | Llama3 などのモデルでは、人間のフィードバックを利用して「より人らしい回答」を生成できるようになっている。AIが“指示を理解する力”を持つ時代になった。 |
| 推論能力と効率化(Reasoning Models) | 「Chain-of-Thought(思考連鎖)」や reasoning-effort の制御により、AIが問題を段階的に考えるようになった。 | 難しい質問のときは「ゆっくり考える」、簡単なときは「早く答える」など、AIが自分の思考リソースを調整できるようになっている。 |
| 視覚言語モデル(LVLMs) | LLM に視覚入力を統合し、画像理解と文章生成を同時に行う。GPT-4o や Gemini などが代表。 | これにより、AIは「画像を見て説明する」「図を読んで答える」など、人間に近い多モーダル理解を実現している。 |
| LVLMの課題と改善 | 視覚エンコーダの改良(MoF構造)、高解像度画像対応、冗長なトークン削減など。 | モデルがより細かい視覚的特徴を把握できるようにすることで、誤認識を減らし、推論の一貫性を高めている。 |
| Agent AI(ツール使用能力) | LLMが外部ツール(Web検索、Python実行など)を活用して課題を解決する能力。 | AIが単なる回答生成から、「実際に行動して問題を解決する」段階に進化。まるで人間のアシスタントのように動けるようになっている。 |
【Welcome Party🎉】
国際交流ホール3でウェルカムレセプションが開かれ、
参加者同士で食事をしながら研究の経験や話題を共有しました。
お寿司もデザートもとても美味しかったです〜! 🍣🍰


【2025/10/23 (木) 3日目】
この日には、自分の研究と関連する発表が多く行われ、
多くの発表者の方々と意見交換をすることができました。
その中で多くのことを学び、人と人との交流から新しいアイデアが生まれることを改めて実感しました。✨
【Session : Knowledge Management】
#222 Code Quality and Difficulty Aware Programming Knowledge Tracing
Jiajia Li (Shenyang Aerospace University); Yuxi Zhu (Shenyang Aerospace University); Yifei Zhang (Shenyang Aerospace University); Cunqian Yu (Shenyang Aerospace University); Liang Zhao (Shenyang Aerospace University); Fang Liu (Shenyang Aerospace University)
この研究は、学生がプログラミング課題に取り組む際の「コードの品質(Code Quality)」を分析し、学習過程をより正確に理解することを目的としている。
プログラムが正しく動くだけでなく、「どのように書かれているか」「どの部分に工夫や誤りがあるか」という観点から、学習者の理解度を評価しようとしている点が印象的だった。


| 項目(項目名) | 重要ポイント(Key Points) | 簡単な説明(Simple Explanation) |
| 研究目的 | プログラミング教育において、単に「正解・不正解」だけでなく、コードの品質(Quality)と問題の難易度(Difficulty)を考慮して学習者の知識状態をより正確に予測することを目的とする。 | 従来の知識追跡は「答えが合っているか」に依存していたが、本研究では「コードの良さ」と「課題の難しさ」を組み合わせて、学習者の本当の理解度を推定できるようにしている。 |
| モデル構成(PSEC・CQEQモジュール) | コード品質を定量化するために、PSEC(Programming Skill Enhanced Code)とCQEQ(Code Quality Effect Quantifying)の2つのモジュールを設計。 | これらのモジュールにより、学習者が書いたコードの品質を数値化し、モデルが「どの程度良いコードか」を判断できるようにしている。 |
| 難易度統合モジュール(DFM) | 問題やスキルの難易度を統合的に考慮するモジュール(DFM: Difficulty Fusion Module)を導入。 | 学習者は一般的に「近いレベルの難易度」に最も影響を受けるため、DFMを用いることで、難易度差を反映したより現実的な予測が可能になる |
| 技術的特徴 | DeepSeekなどの事前学習モデルを用いて自動的にコード品質を評価し、学習者の能力推定に組み込む。 | AIがコードを読んでスコアを付けることで、評価の客観性を保ち、人間教師による主観的評価を補完する。 |
| 実験結果 | BePKTデータセットにおいて、AUC 0.7420、ACC 0.7825と既存手法を上回る性能を達成。 | コード品質と難易度の両方を考慮することで、学習者の将来のパフォーマンスをより高精度に予測できることを実証した。 |
| 今後の展望 | コードのスタイルや構造的特徴に加え、学習者の行動ログ(キーボード入力、マウス動作など)も統合する方向を検討。 | プログラミング行動全体をモデル化することで、より多面的な学習理解支援を実現することを目指している。 |
#219 SectorE: Knowledge Embeddings with Representing Relations as Annular Sectors
Huiling Zhu (South China Normal University); Yingqi Zeng (South China Normal University)
SectorE の研究では、知識点(concepts)の関係を「扇形の領域」で表現しており、知識間の構造的なつながりを幾何的に捉えるアプローチが用いられている。
もしこのような幾何的な関係表現を、プログラミング知識追跡(Knowledge Tracing)に応用できれば、知識点同士の関係をより精密に扱えるようになり、モデル性能の向上につながるかもしれない。
自分の研究とも組み合わせられそうで、今後の発展がとても楽しみだと思った。



| 項目(項目名) | 重要ポイント(Key Points) | 簡単な説明(Simple Explanation) |
| 研究目的 | 知識グラフ(Knowledge Graph)における関係表現を改善し、不完全な知識間リンクをより正確に予測する新しい埋め込みモデル SectorE を提案。 | 知識グラフは「A–B の間にどんな関係があるか」を記述するが、情報が欠けていることが多い。SectorE はその関係性をより自然に表現・補完することを目的としている。 |
| モデル構成 | 関係を「線」ではなく「環状セクター(annular sector)」として表現し、極座標(polar coordinate)空間上でモデリング。 | 実体(entity)は点として、関係(relation)は円環状の領域として表す。ある点がその領域内に入れば、その関係が成り立つと判断する。 |
| 実体と関係の表現 | 実体は位置ベクトル+変換関数(transformational bump)として定義。関係は角度範囲と半径で定義されるセクター領域。 | 実体ごとに関係方向と距離を調整できるため、複数の関係を同時に表現可能。動的な埋め込み構造を持つ。 |
| 特徴と利点 | 極座標ベースの表現により、対称性(Symmetry)、反対称性(Anti-symmetry)、逆転性(Inversion)、包含性(Subsumption)といった複雑な関係パターンを同時に捉えることが可能。 | これまでのモデルでは困難だった「上位・下位」「親子」「逆関係」などの複雑な関係性を統一的に扱える。 |
| 実験結果 | 複数の標準知識グラフデータセット(WN18RR、FB15k-237など)で高いリンク予測精度を達成。 | 既存モデル(TransE、RotatEなど)と比較して、構造的関係の表現力と再現率で優れていることを示した。 |
| 今後の展望 | 層次的・多関係型知識グラフへの拡張、および自然言語理解タスクへの応用を検討。 | 関係を幾何的に表現する方法を教育・医療・社会ネットワークなど他分野にも応用可能と考えられている。 |
【Banquet】
会場は Hotel Okura Kyoto(ホテルオークラ京都) で開催されました。
格式高い雰囲気の中で、美味しいフレンチ料理を楽しみながら、研究者同士の交流を深めることができました。
料理の盛り付けも美しく、特にメインディッシュとデザートが印象的でした。🍷✨




今日の会場では京都伝統的なお菓子阿闍梨餅が配られていました美味しかったです!
宿泊先の近くで食べた明石焼きです。外はふわっとしていて、出汁と一緒に食べるととても美味しかったです! 😋


【2025/10/24 (金) 4日目】
#241 AEKT: A Multi-Dimensional Knowledge Tracing Model Integrating Student Cognitive Ability and Knowledge Acquisition
この研究では、学習者の「認知能力(Cognitive Ability)」と「知識獲得(Knowledge Acquisition)」の2つの側面を同時にモデリングし、
二重マトリクス構造(Dual-Matrix)によって学習の多次元的なプロセスを表現していた。
残念ながら、私の発表と同じ時間帯だったため、詳細な実装や実験設定を直接聞くことはできなかったが、
発表者の研究者と連絡先を交換することができたので、今後この分野について意見交換できればと思う。
【後記】
福岡に戻る途中、鴨川のほとりを通りました。
夕日に照らされた鴨川は本当に美しくて、思わず足を止めてしまいました。
夕食を食べる時間がなく、とてもお腹が空いていたので、京都駅で「伊右衛門弁当」とお茶のセットを買いました。
とても京都らしい味わいで、旅の締めくくりにぴったりでした。


最後に、これまでご指導くださった荒川先生と峯先生に心より感謝申し上げます。
研究の過程で本当に多くのご助言とサポートをいただきました。
峯先生は学会当日も会場に来てくださり、研究者の方々との交流をサポートしてくださったり、
今後の論文の方向性について一緒に考えてくださったりと、本当に心強かったです。
また、汪君にも京都滞在中たくさん助けていただき、写真もたくさん撮ってもらいました。
これからも研究を頑張っていきたいと思います。✨